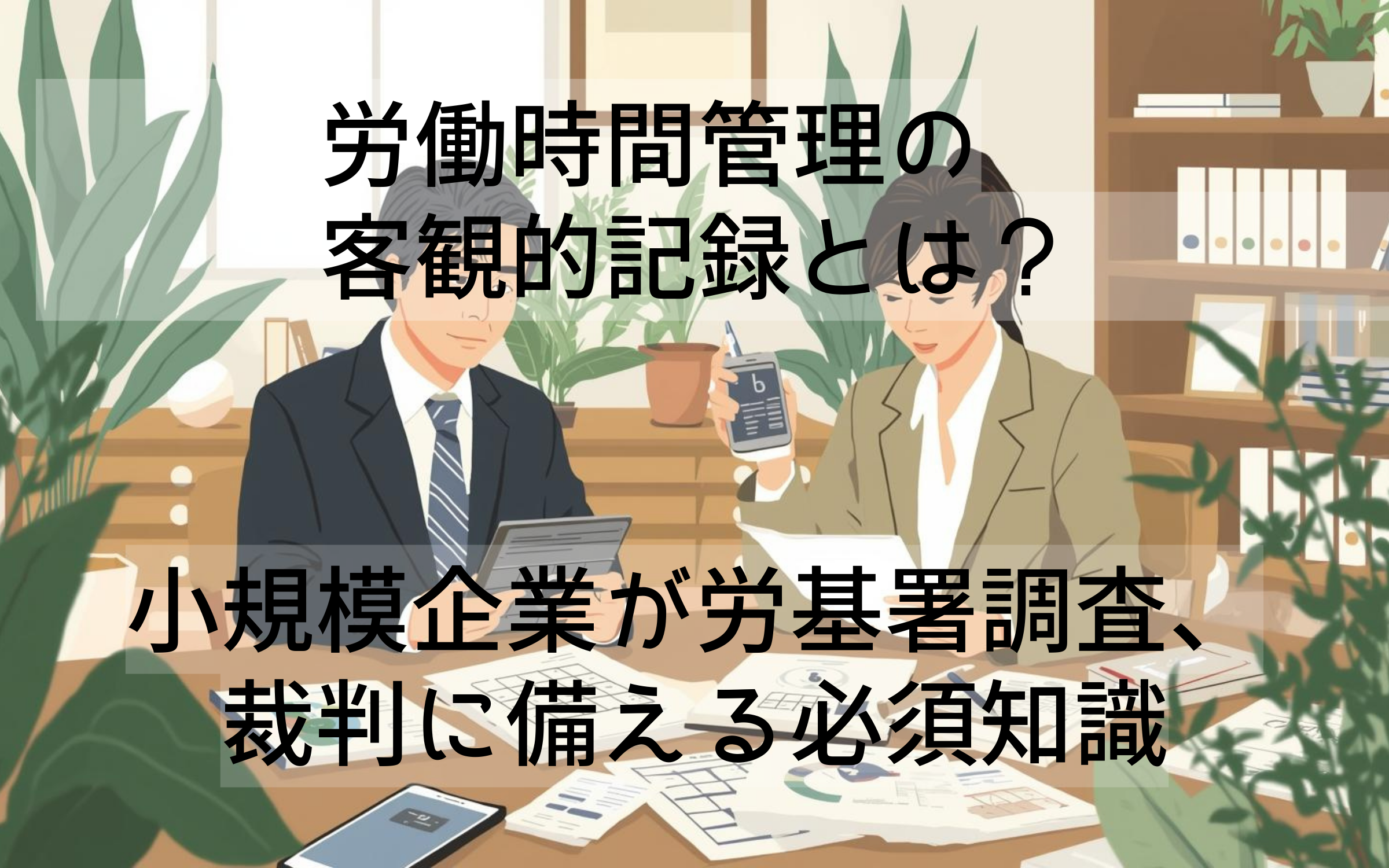人口10万人未満の地方都市にある従業員50名以下の中小企業にとって、労働時間管理は後回しにされやすいテーマです。
人手不足の中、現場優先で仕事が回り、勤怠管理は「タイムカードを打っているから大丈夫」「昔からこのやり方で問題なかった」という感覚で運用されているケースも少なくありません。
しかし近年、労基署調査や未払残業代請求の場面では、労働時間管理の客観的記録が厳しく問われるようになっています。
これは企業規模に関係なく、避けて通れない必須知識です。
目次
労働時間管理の客観的記録とは何か
労働時間管理の客観的記録とは、使用者の主観や従業員の自己申告に頼らず、第三者が見ても合理的に判断できる記録のことを指します。
代表的なものはタイムカード、ICカード、勤怠システムの打刻記録などです。
厚生労働省のガイドラインでも、原則として客観的な方法による把握が求められています。
特定社労士の実務感覚としても、「客観的かどうか」が調査や紛争の分かれ目になる場面が非常に多くなっています。
勤怠記録があっても安心できない理由
多くの経営者が誤解しているのが、「勤怠記録さえあれば会社が有利になる」という考え方です。
実際の調査や裁判では、勤怠記録が存在していても、それだけで終わりません。
労働者が「私のメモではこうです」「実際はもっと働いていました」と主張した場合、調査は一段階深く進みます。
その際に確認されるのが、PCログ、メールの送信履歴、業務システムの操作履歴などです。
つまり、表向きの勤怠記録と実態がズレていれば、言い逃れはできません。
PCログまで確認される現実と企業のリスク
労基署調査や裁判では、「業務に従事していたかどうか」が重要視されます。
たとえば、タイムカード上は18時退勤になっていても、19時や20時までPCが稼働し、業務メールを送っていれば、その時間が労働時間と認定される可能性があります。
特に小規模企業では「家に持ち帰って作業していた」「上司に頼まれたわけではない」という主張が通らないケースも多く、管理が曖昧なほどリスクは増大します。
特定社労士としては、ここを甘く見ている企業ほど、後で大きなダメージを受けやすいと感じています。
自己申告制が抱える落とし穴
自己申告制の勤怠管理を採用している企業も多いですが、運用を誤ると非常に危険です。
申告内容をチェックせず承認している、残業申請を出しづらい空気がある、申告と実態が乖離しているといった場合、客観性は否定されます。
「申告していない=働いていない」という理屈は通用しません。
むしろ、申告させない仕組み自体が問題視されることもあります。
制度そのものより、実態と整合しているかが問われます。
小規模企業が今すぐ押さえるべき対応ポイント
まず重要なのは、「記録を取っているか」ではなく、実態を反映した記録かどうかを見直すことです。
打刻と実際の業務開始・終了時刻が一致しているか、サービス残業が前提になっていないか、管理職が暗黙に時間外業務を指示していないかを点検する必要があります。
また、PCログや業務履歴との整合性を意識した運用に変えていくことが、将来のリスク回避につながります。
特定社労士の視点では、労働時間管理は「仕組み」と「運用」をセットで整えなければ意味がありません。
まとめ:客観的記録は企業を守る最後の防波堤
労働時間管理の客観的記録は、労基署調査や裁判において企業を守る最後の防波堤です。
勤怠記録があっても、労働者のメモやPCログと矛盾すれば、企業側が不利になる現実があります。
小規模企業だから見逃される時代はすでに終わっています。
今の運用が「説明できる状態かどうか」を冷静に見直すことが、将来の大きなトラブルを防ぐ最も確実な一歩です。
筆者プロフィール
泉 正道(Masamichi Izumi)
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2025年現在、延べ100社以上の中小企業を支援。
採用・定着・労務に関する相談は累計2,000件超。
徹底的な伴走支援で、中小企業の採用定着を「仕組み化」する事を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。
*姫路播州採用定着研究所
*C&P社労士法人 公式サイト
*Facebook